2025年10月16日、17日の2日間、総務企画防災常任委員会の視察で静岡県三島市及び焼津市に訪問しました。
こちらは公費での参加となります。
以下は、視察レポートになります。
記事作成:2025/10/25
【視察内容】
1日目は三島市役所にて、『移住・定住推進施策』についてのレクチャーを受けました。東京までの距離は足利市とあまり変わりませんが、新幹線の停車駅であることや富士山を望むまちのイメージのためか、移住・定住の実績があります。
どこでも同じような対策は取っているのに。。。というのが正直な感想です。
なお、一番の成果は、市役所庁舎の候補地2か所について、市民1万人にアンケートを実施したということでした。
2日目は、焼津市役所にて、『公共施設マネジメント推進』についてのレクチャーを受けました。老朽化した公民館や学校の利活用の話が中心でした。建てて4年目という新庁舎の見学もしましたが、お金がなければここまでできない!という設備でした。足利の方が現実は厳しかったです。
以下は、視察後に提出したレポート(原文)になります。
字数制限がありますので、個人の感想は一番下にまとめています。
⇒令和7年度の各常任委員会の視察報告書一覧はこちら※準備中です
○静岡県三島市
移住・定住推進施策について
【所 見】
三島市は、理想的な移住先として上位にランクした実績があり、直近4年間の県外からの移住者は年間130~171人で推移している。富士山を望む景観や伊豆の玄関口という立地からレジャー資源にも恵まれており、また、東海道新幹線の停車駅で、ひかりで品川駅まで37分という高い交通利便性は首都圏在住者に広く知られているため、転職せずに移住するというマインドが働きやすい。
同市の支援制度は、住宅取得補助、リフォーム補助、移住・就業支援金、結婚新生活支援、出産祝金などを体系的に整理し、『住むなら三島』という統一ブランドで発信している。市民も対象とする住宅補助や利子補給制度など、対象範囲の広さと分かりやすい見せ方が特徴である。こうした制度の網羅性と発信の一体感が、支援が厚いとの印象を与える要因といえる。
一方、ファミリー向け中古住宅の価格は本市に比べ4〜5割高く、新幹線通勤には年間90万円を超える交通費負担が生じる。補助金による誘因には限界があり、沼津市との連携によるお試し宿泊や、移住者自身が企画するイベントなど、金銭以外のアプローチを重視する方向にあるというのは他自治体と同様だ。
振り返って本市を見ると、すでに空き家バンク、通勤補助、出産祝金など実効性のある支援を実施している。首都圏へのアクセスも良く、特急料金や住宅購入費用は三島市よりも割安といえる。課題は「見せ方」と「発信の担い手」である。『燕の下』の情報発信はイベント告知が中心で、移住者自身のリアルな生活発信が少ない。定期的に移住・定住者にざっくばらんなインタビュー動画を掲載したり、個人のSNS発信を市が公式に再投稿するなど、移住・定住者の暮らしの実感が伝わる情報発信体制の構築が望まれる。移住希望者が直接個人にアクセスし、本市での暮らしを身近に感じられるようにすべきである。
本市は、隣に財政が豊かで子育て支援に手厚いイメージの太田市があるため、支援の金額では勝負しにくい。しかし、遠くの山々や渡良瀬川の景観、南北で趣の異なる街並みなど、他市にない「暮らしの豊かさ」「通勤の現実的利便性」「文化的奥行き」を軸にした情報発信とブランドづくりが求められる。“伝わる形に見せる”ことが、今後の移住・定住促進の鍵となる。
余談だが、耐震補強工事を施したレトロな本庁舎には懐かしさを感じた。本庁舎建替えの候補地について、1万人にアンケートを実施したという発言があると、議員一同から感嘆の声が上がった。決定前に民意を反映させようという姿勢は素晴らしい。
○静岡県焼津市
公共施設マネジメント推進について
【所 見】
老朽化した公共施設の床面積の削減や長寿命化、上下水道等インフラ設備の更新は全国的な課題である。焼津市では、延べ床面積を40年間で23.5%削減する目標を掲げている。この公共施設マネジメントの目玉として説明を受けたのが、和田地域交流センター『わかしお』である。老朽化し耐震性能のない公民館は取壊し、児童生徒の減少により余剰が出来た小学校の校舎をリニューアル。公民館、小学校、放課後児童クラブを複合化し、多世代の人が交流できる地域の拠点とするものである。
本市では2055年までに延べ床面積42.2%の削減を目標に掲げ、公民館の集約、公立小中学校の再編を控えている。特に直近で廃校が決定している過疎地域では地域の文化や交流拠点が失われるのではないかという危惧感もある。こうした複合化の取組により、過疎地域であっても地域の連帯や交流の拠点を維持できる可能性を感じた。
ただし、焼津市においても課題はある。すべての地域で同様の複合施設整備が可能なわけではなく、また取壊しを決定する際には、跡地の利活用方針も併せて検討しておくべきだったという。跡地が市街化調整区域に含まれる場合、利活用に制限が生じ、市民に具体的なビジョンを示しにくい点は、本市にも共通する課題である。
研修後は新庁舎を案内してもらった。海が近いため、津波対策から1階はイベントスペースだけで2階以上が執務エリアになっている。庁舎横には立体駐車場があり、市民課など市民が多く訪れる窓口のある庁舎2階に接続している。エレベーターに加え、エスカレーターまであることに度肝を抜かれた。聞けば、海産物を中心とするふるさと納税の返礼品に人気があり、寄付額が年間100億円にも上るという。財源が豊かだからこそ実現できる庁舎の建替えに思えた。議場の奥はガラス張りになっており、富士山を望むこともできる。財源の問題、削減目標ともに本市の方がシビアな課題に直面しているため創意工夫が必要だ。
【三島市のフォトギャラリー】

三島市役所正面玄関前
1960年に建設され、2025年現在で築65年!耐震補強の鉄骨が張り巡らされている。

足利市役所の別館を思わせるレトロな階段

マホガニーを基調としたレトロな議場

現在は使われていない書記席があるのも昔ながらの造り

三島市役所でレクチャーを受けている様子
【焼津市のフォトギャラリー】

焼津市役所 2021年7月末に完成、立体駐車場は23年3月に完成予定。
現庁舎の解体を含めた総工費は約98億5000万円。
正面玄関の前には焼津温泉の足湯と温泉スタンドがある。
駅前にも温泉付きのビジネスホテルやマンションがあった。

1階は市民の憩いのスペース、時々イベントも開催される。

1階から2階へはエレベーターの他にエスカレーターもある。

本庁舎の横には4階建ての立体駐車場。
市民課などの窓口のある2階に接続されている。
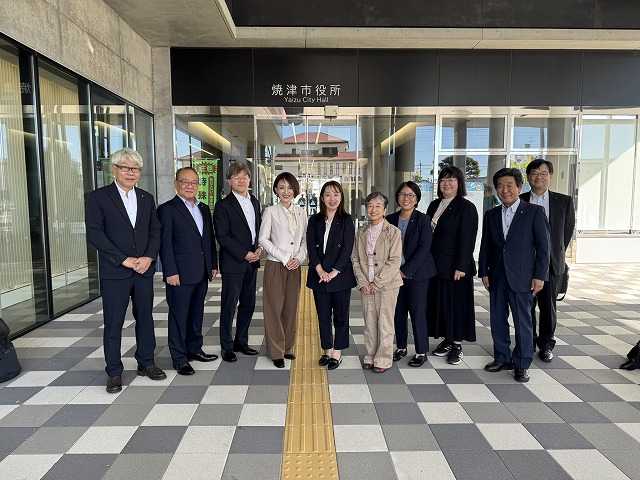
1階玄関前で記念撮影。

明るくモダンな議場。

議長席の後ろはガラス張りに、目の前には焼津港。

正面奥には富士山を望める。

焼津市役所でレクチャーを受けている様子。
小沼みつよのSNSはこちら
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
会派『足利志士の会』のSNSはこちら
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
